今回の国立大学法人法「改正」案では、運営方針会議の設置を義務づけられる大学(特定国立大学法人)以外の国立大学を含めて、財政にかかわる「規制緩和」を認めている。
具体的には、次の二つのことを定めている「国立大学法人法の一部を改正する法律案(概要)」)。
- 長期借入金や債券発行ができる条件を緩和し、施設の整備などばかりではなく「先端的な教育研究の用に供する知的基盤の開発又は整備」についても可能とする。
- 土地等の第三者への貸付けにあたって全般的計画が文科大臣の認可を受けている場合には個別の貸付について認可を要せず届出でよい。
この規制緩和は、国立大学の学長にとっては、とても魅力的に思えることであろう。この点を理解するためには、国立大学の財政的な状況を知る必要がある。
2004年の国立大学法人化以降、国立大学の基盤的経費(運営費交付金)は年々1%ずつ削減された。さらに2016年度からは基盤的経費のうちの10%程度を「重点支援枠」として一定の評価指標に基づいて再配分し、文科省の意向に忠実な「改革」を行った大学については予算を増やし、そうではないと評価した大学の予算は削減することとなった。
一方で物価は高騰し、大学は慢性的に予算不足に悩まされている。その結果として、光熱費(電気代)を節約するために図書館を早く閉館にする(「阪大附属図書館、電気代高騰で時間短縮…卒論にも影響か」)、メンタルな問題を抱えた学生の「命綱」であった保健診療所を廃止するようなことが生じている(「京都大学保健診療所を廃止しないで下さい」「京都大学の保健診療所が突如廃止のウラ」)。
個々の大学執行部の責任も重大だが、こうした事態の前提には政府による基盤的経費の削減が存在する。政府は、学生の就学環境や福利厚生を学生にとって望ましい形で維持するために予算を責任を放棄しつつあるのだ。これに対して、国立大学協会ですら「基盤的経費の拡充」を求めて次のような要望を文科大臣宛に提出した。
国立大学がその機能と役割を更に強化・拡張し、今後も国民の期待に応え、社会の発展に貢献するための未来への投資として、基盤的経費である運営費交付金の拡充を求めます。特に、運営費交付金の一部を毎年度、共通指標に基づき傾斜配分する仕組みは、中長期的な見通しを持った責任ある大学経営を困難にするのみならず、各大学が一律に指標の評価値向上に舵を切らざるを得ず、ひいては国立大学の多様性を損なう恐れがあることから見直しを求めます。(国立大学協会会長永田恭介「令和5年度予算における国立大学関係予算の充実及び税制改正等について(要望)」2022年10月3日)
だが、文科省、あるいはその背後に鎮座する財務省は、決して基盤的経費を増やそうとしない。むしろさらなる削減、さらなる「重点支援枠」の拡大を図ろうしている。軍備拡張のためには財源を度外視しても予算を大幅に増大させようとしているにもかかわらず、国立大学に対しては「予算がない」と頑なな姿勢を貫いている。
この政府の頑なな姿勢が、国立大学の運営に大きな歪みをもたらしている。そこで政府は頑なな姿勢それ自体は変えずに、「財源の多様化」というような言葉でほかに財源を求める方向に大学を誘導している。「稼げる大学」という言葉も、こうした文脈のなかで登場する。だが、国立大学はそもそも営利を目的とした組織ではないし、そのために税法上の優遇措置を受けてもいる。私立大学を経営する学校法人でも営利事業への関与にはさまざまな制限がかけられている。したがって、「稼ぐ」手段もおのずから限定されることになる。
資金難に直面した大学側の求める打開策のひとつは、クラウドファンディング(クラファン)である。新型コロナ感染症拡大のさなかの2020年、京都大学附属病院長は手術室の陰圧室工事のためにクラファンをはじめ(「高度先端医療と感染症対策の両立で、コロナ禍でも多くの命を守る」)、今年、金沢大学基金・学友支援室は学生向けのトイレの整備・改修ためにクラファンをはじめた(「金沢大学生の一人ひとりが安心して使えるトイレを少しでも増やしたい」)。クラファンをすること自体は、社会から研究者への期待の所在を知ると同時に社会への説明責任を果たすことにもつながりうる。だが、トイレのような基本的な設備を改修する費用までクラファンに委ねるべきか、政府が責任をもって公費(税金)をあてるべきことではないのか。しかも、クラファンで集めることのできる金額には制限もある。京都大学附属病院は3000万円の目標を越えて6000万円を集めたが、億には達していない。金沢大学のトイレ改修は合計で1億円かかる見込みであるものの、クラファンの目標額はその10分の1、1000万円である。億単位のお金をクラファンで集めるのは難しいといえる。
もうひとつの方向性は、特許など知的財産によるライセンス収入、あるいは知的財産を生かしたベンチャー企業の創設や、企業から寄附金を受領するなどの産学連携である。大学が研究開発を通じて企業に利益をもたらし、逆に企業から大学への投資を呼び寄せよというわけである。第二次安倍政権の成立以来、こうした産学連携への圧力が全国津々浦々の大学に対してかけられてきた。だが、研究とは、文系と理系とを問わず、試行錯誤の末にオリジナルな知見や新たな技術を生み出せるかもしれないという試みであり、一種の「賭け」の要素をはらまざるをえない。「確実に勝てる馬券」が存在しないように、「確実に稼げる研究」など存在しない。そのために教育研究成果の活用による収益の獲得は、うまくいく時もあれば、そうでない時もある。
結局、巨額の資金を調達するには、長期借入金や債券(大学債)の発行、すなわち借金が必要という方向に大学は追い込まれる。国立大学が法人化した当時から、長期借入金や大学債の発行は可能だった。ただし、附属病院の施設整備など施設から直接的に業務収入を見込むことができて、確実に償還できる場合にかぎられていた。ところが、2020年6月に政令改正により、直接的な収入を見込めない施設のためにも大学債発行が可能とされた。償還の財源にも新たな施設からの収入だけでなく、大学全体の余裕金(寄附金など)をあてることができるようになった。
この規制緩和を受けて東京大学はさっそく大学債を200億円発行、償還期間は40年で毎年の利回りは0.823%とされた(「東京大学FSI債(投資家向け情報)」)。その後、確認できているかぎりでも、昨年から今年にかけて次のような起債が行われた。
- 「大阪大学生きがいを育む社会創造債」総額300億円、償還期間40年、年利1.169%、
- 「筑波大学社会的価値創造債」総額200億円、償還期間40年、利率1.619%
- 「東京工業大学 つばめ債」総額200億円、償還期間40年、利率1.800%
- 「東北大学 みらい創造債」総額100億円、償還期間40年、利率1.879%
- 大学債を起債して、もしも毎年の利払いを行うことができず、債務不履行に陥った場合に、誰がどのように責任を取るのか。企業の代表取締役のように、学長を含む運営方針会議委員が個人として私財を投げ打っても経営責任をとるのか?
- もしも運営方針会議委員に対して個人としての経営責任をとらせる制度設計でないとすれば、誰がどのように責任をとるのか。教職員の人員削減や労働条件の改悪、学生の授業料値上げで損失を埋め合わせることをしないと断言できるのか?
- 昨年の大学設置基準改正はなぜ行われたのか? 学生たちにとってのキャンパス空間の意味をどのように考えているのか? 体育館、運動場、学生控室、寄宿舎、図書館閲覧室などはなくても問題ないと考えているのか?
- 今回の法「改正」による規制緩和措置は、大学の公共性、公益性を大きくそこなう可能性があることを認めるか? もしも認めないならば、大学設置基準が設けられている意味や、これまで大学債の起債に制限がかけられてきた理由を説明せよ。もしも認めるならば、大学を経営的に困難な状態に陥らせている要因をとりのぞいて大学の公共性、公益性を立て直すために、基盤的経費の総額を国立大学法人化当時の水準に戻し、傾斜配分をやめよ!
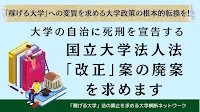
野原光(広島大学・長野大学名誉教授、元長野大学学長)と申します。
返信削除第2弾、拝読しました。もともと持っていた疑念の一つが解けた気がしました。
日本の大学政策が、「市民」の形成には一顧だに払わず、国際競争を勝ち抜く技術「人材」(とその兵隊)の育成を狙っており、有無を言わさず、しかも大急ぎでこの方針を貫徹するために、大学のガバナンス構造を変える。粗っぽく言えば、このように国策の趨勢を理解していましたが、拝読して、それだけではないことに気づかされました。
低成長と投資先の不在に苦しむ日本企業は、有利な企業活動の場を求めて右往左往しています。もし大学界隈が、こうした新たな投資先になりうるなら、これはもっけの幸いです。当初は、大学債とか、土地の貸し付けとかは、自己資金の乏しい大学を独立採算化できるように、無理やりその手段を用意するということと理解し、それにしても、何で大学債と、土地貸付が突出して出てきたのかといぶかっていました。しかし駒込さんのご指摘で、なるほどと腑に落ちました。大学債と土地の貸し付けは、大学の資金調達の「手段」を提供したにとどまらなかった。それ自身が企業の投資対象の創出という、政府・財界の「目的」でもあるということになります。
そうした大学の企業化の結果、学生の日常空間はどうなっていくのか。若者にとっては、なんのためにという目的・手段連関では説明できないような、つまり機能別のゾーン分けでは存在余地のない、なんとなく胡散臭い自由空間が、「市民」としての自己形成にとって不可欠です。ところがご指摘のように、それがどんどん削られていきます。これは若者の自己形成にとっての致命傷になってしまいます。
改めて恐ろしさを痛感しました。我々は、大学を企業の投資活動の草刈り場にしてはならない。
貴重な着眼点を教えていただき感謝します。